蓼科神社秋祭用奉納屋台および雅楽器一式



蓼科神社里宮は享保期に現在の地に移され、その頃より例祭9月20日には芦田郷中の獅子舞と道中行列が奉納され、例年地元の若衆が祭事係を請けていた。この屋台は江戸時代の中頃、小諸藩の推挙で造られ、城内や城下の領民に安息の一助を与えたと伝えられる。その作風は、総檜材で黒漆塗りの彫刻、彫金金具飾り、緞帳(どんちょう)は金・銀糸の刺繍(ししゅう)で色彩豊かに花鳥・狛犬(こまいぬ)が描かれている。屋台柱の伸縮に滑車を利用した中二階造りは珍しく、平成2年には町指定文化財に指定されている。
三頭(みかしら)獅子の流れと譜は、三河派に類し、親子獅子の獅子頭は漆張子作りで稀少。楽器は大小の太鼓、三味線、大皮、横笛があり、巻絵漆塗りで雅やかである。約300年前からの伝統芸風が継がれ屋台とお囃子(はやし)に特有の趣がある。
現在、祭りは毎年9月に行なわれている。
地図
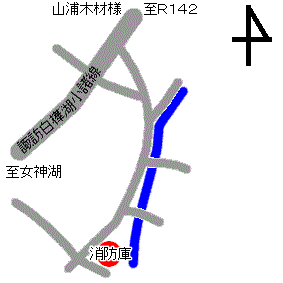
所在:立科町大字芦田491
秋祭の時だけみることができます。(古町区消防庫前から出発)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
ご意見ありがとうございました。








更新日:2023年03月31日